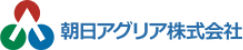農業用肥料PRODUCTS

あ行
- 秋落ち水田アキオチスイデン
- 収穫間際になって、急激に水稲の下葉が枯れ上がり、穂も成長せず収量が少なくなるという現象が起こる水田のこと。
硫化水素の発生により水稲根に障害を起こすことが原因です。遊離酸化鉄の溶脱が進んだ老朽化水田で起こります。
関連リンク
- アルカリ分アルカリブン
- 肥料法における保証成分で、石灰質肥料などの肥料中に含まれる可溶性石灰の量、または可溶性石灰と可溶性苦土の量を、酸化カルシウムに換算した量のこと。日本の土壌は酸性の火山灰土壌が多く、酸性土壌のpH矯正の際の目安にもなります。アルカリ分が高いほど、酸性矯正能が高いです。
- 塩基置換容量(CEC)エンキチカンヨウリョウ
- 保肥力の指標であり、陽イオン交換容量ともいいます。土壌が陽イオン(塩基)を保持できる最大量を示す値のことで、土壌診断の結果として出てくる値です。
塩基置換容量が大きい程、保肥力が高いといえます。また土壌中に有機物や腐植が多いと、陽イオン置換容量は大きくなります。
か行
- 過繁茂カハンモ
- 栄養成長ばかりが進んでいる状態のこと。
肥料、特に窒素質肥料を必要以上に与えると、栄養成長(葉、茎、枝の成長)が続き生殖成長(花、種子、果実の生産)への転換ができなくなってしまいます。この状態を過繁茂と呼びます。
- 加里カリ
- 植物が最も必要とする栄養素である、肥料三要素のひとつ。肥料では、酸化物の酸化カリウム(K2O)を加里成分としている。
加里はイオン化傾向が高く、加里塩類のほとんどのものが水に溶け、容易に作物に吸収利用されます。有機質肥料に含まれる加里は、陽イオンとして有機物の官能基とイオン結合した形なので、これも速やかに溶出し、肥効を示します。
加里が過剰だと拮抗作用により苦土欠乏を引き起こすため、施設栽培や多量の厩肥の施用には注意が必要です。
はたらき : 植物体中のでん粉、糖分、たん白質の生成を助け、体内での移動や蓄積にも関与している成分です。加里の働きには、(1)開花結実の促進 (2)日照不足時に生育を促す (3)水分の蒸散作用を調節 (4)根の発育促進などがあります。窒素に次いで植物の吸収量の多い養分です。
- キレートキレート
- キレートとは「カニのはさみ」を意味し、栄養分となるミネラルを有機物中の官能基ではさみの様に結合する形を言います。薬剤ではEDTAが有名であり、液肥では鉄や銅などのキレート物を原料として使用しています。キレートの形になると、金属の沈殿が防止され、溶解性が高まります。
土壌中では堆肥などに含まれる腐植酸によるキレート効果で微量要素などの成分を吸収しやすくなるとともに、肥料効果が高まるといわれています。
関連リンク
さ行
- 側条施肥ソクジョウセヒ
- 施肥方法のひとつ。
肥料を苗の根の近くに施すことにより、初期の発育を活発にし、肥料の流亡を抑えます。
機械施肥によく用いられ、特に水稲で省力、施肥量低減を目的に増加しており、主流の施肥法となっています。
側条施肥機に使用できる肥料は、粒度、硬度、水分、安息角、吸湿性などの厳しい基準をクリアすることが求められていますが、当社の有機アグレット肥料は側条施肥にご使用いただけます。
関連リンク
- 速効性肥料ソッコウセイヒリョウ
- いわゆる速ぎきの肥料で、土壌や葉面に施肥したとき速やかに作物に吸収利用され、肥効を現す肥料のこと。
速効性肥料の大部分は水溶性で、通常の無機質肥料(化学肥料)はほとんどこれに属します。ただし、土壌や周囲の環境要因、成分、組成、作物養分吸収チャネル等により養分の移動、吸収性は変動するので、要素欠乏発生時の対処としては要因をよく解析して対応する必要があります。
た行
- 炭素率/C/N比タンソリツ/シーエヌヒ
- 土壌や有機物中の炭素(C)と窒素(N)の比率のこと。
有機物の腐熟の度合いを示すことにも使用され、未熟のものは高く、十分に分解が進んだものは低くなります。未熟な有機物を土壌に施用すると初期分解産物として有機酸等の発芽障害物質を生成したりします。
炭素化合物の割合の高い炭素率が30以上の有機物を施用すると、土壌中酸素が減少し還元状態となったり、微生物と植物との間で窒素の取り合いが起こり、植物が窒素飢餓を起こす可能性があるので注意が必要です。
- 団粒構造ダンリュウコウゾウ
- 土壌の単一粒子が集まって大きな粒子の集合体になっている構造のこと。
団粒は丸みを帯びており、有機物・石灰の多い表層土に見られます。堆肥等の有機物を施用することにより繁殖した微生物の菌糸や、植物の根からの分泌物などが接着剤のはたらきをして団粒構造の形成が促進されます。
団粒の発達した土壌はいわゆるふかふかの土で、孔げきが多く、保水力に優れ、空気の流通もよい、植物の生育にとって好ましいものです。強く圧すると崩れてしまうため、注意を要します。
- 窒素チッソ
- 植物が最も必要とする栄養素である、肥料三要素のひとつ。
窒素は有機物、尿素、アンモニア、硝酸などの形で土壌に施されます。施用された有機物は微生物により分解されアンモニア態窒素となり、畑地条件ではさらに亜硝酸を経て硝酸態窒素になります。
植物は低分子のアミノ酸なども吸収できますが、ほとんどはアンモニア、硝酸の形で窒素を吸収しています。畑作物では好硝酸性作物が多いです。
硝酸態窒素は、利用され易くまた低温でも吸収されやすいですが、陰イオンの為、表面が陰電荷を帯びた土壌コロイドとは反発し、土壌から流亡しやすい特徴があります。
アンモニア態窒素は陽イオンで土壌に保持され易く土壌からの流亡が少なく、硝酸態窒素に比べ吸湿性が低く扱いやすいなどの特徴があり、水稲では主体となる窒素源となります。
有機態窒素は有機物中のたん白質が分解されアミノ酸、アンモニアに分解されてから吸収されるため緩効的です。
はたらき:植物の細胞原形質の主成分であるたん白質を構成し、植物の生育にとって最も重要な要素です。(1)細胞の分裂や増殖 (2)根、茎、葉の生育を促す (3)炭酸同化作用を盛んにする などのはたらきがあります。過剰に施すと、過繁茂を引き起こします。
- 土壌の三相分布ドジョウのサンソウブンプ
- 土壌は、固相、液相、気相の三つの相から成り立っており、各相がそれぞれ占める割合のこと。
作物の良好な生長には、土壌粒子の間に、水分と空気がバランス良く分布していることが必要です。有機物を施用した土壌では微生物の菌糸などの接着効果で団粒構造が発達し、気相、液相の割合が増えてきます。また、堆肥やピートモスなども通気性や保水力を物理的に高め、良好な三相分布の形成に寄与しています。
- 土壌微生物ドジョウビセイブツ
- 土壌中に生息する微生物の総称のこと。
放線菌、糸状菌、原生動物、線虫類などが含まれます。
窒素成分をアンモニア態あるいは硝酸態などの植物が利用できる形に変換するなどのはたらきを持っています。また有機物分解により腐植や団粒構造を作り、土壌環境を整える上でも重要な役目をしています。
な行
- 流し込み施肥ナガシコミセヒ
- 水田の水口から灌漑水と一緒に液体肥料や専用の固体肥料を流し込む追肥方法のこと。
その年の気象や水稲の生育状態に応じて施肥することができ、機械を使うことなく作業できるため、省力・低コスト施肥技術として利用されています。
関連リンク
は行
- pHピーエッチ
- 酸度(水素イオン濃度)のこと。
水素イオンの濃度が高いほど酸性、低いほどアルカリ性になります。pH7(中性)を境に、数値が小さくなる程強酸性、数値が大きくなる程強アルカリ性といいます。
硫酸や硝酸などは酸性を呈し、カルシウムやマグネシウムなどはアルカリ性を呈します。土壌や植物の適正pHは弱酸性~中性なので、極端な酸性やアルカリ性にならないよう、土壌診断等を活用してください。
- 微生物資材ビセイブツシザイ
- 微生物を含有し、微生物の機能を利用して作物の生育や土壌環境の改善・向上を目的として使用される資材のこと。
「土壌などに施用された場合に、表示された特定含有微生物の活性により、用途に記載された効果をもたらし、最終的に植物栽培に資する効果を示す資材」と定義されています。(微生物を利用した農業資材の現状と将来, 1996, 日本土壌肥料学会公開シンポジウム)
政令指定を受けている「VA菌根菌」の他、堆肥化の促進、土壌団粒形成、窒素固定、りん酸の可溶化、土壌病害虫の軽減、植物ホルモン、ビタミンの生成など各種の効果があるとされる資材が数多く市販されています。
関連リンク
- 肥料の三要素ヒリョウのサンヨウソ
- 窒素、りん酸、加里を肥料の三要素といいます。肥料中の三大要素の成分は窒素はN、りん酸はP2O5、加里はK2Oに換算され表示されています。
窒素、りん酸、加里は、植物の必須元素であり三大栄養素と言われ、ほとんどの植物で吸収量が多く、この内どれかひとつが欠けると植物の生育は著しく劣ります。そのため、肥料はこの三要素を中心に成分の構成がなされています。
- 微量要素ビリョウヨウソ
- 植物必須元素で、要求量は少ないが、吸収量が極度に少なくなると、その欠乏症におかされる成分で、マンガン、ほう素、銅、鉄、塩素、亜鉛、モリブデン、ニッケルのこと。
しかしこれらの成分は、ある量を越すと、逆に植物に害を与えてしまいます。
微量要素の欠乏症が生じたときは、葉面散布でも対応可能な場合が多くあります。
- 腐植酸フショクサン
- 土壌に含まれる腐植物質の中で堆肥のエッセンスと言われる黒褐色の酸性物質のこと。土壌腐植をアルカリ可溶、酸不溶物質として分画して得られます。
土壌有機物の代表で、その形は無定形のものから中高分子の化合物までと幅広く、炭素50~60%、水素3~6%、窒素1.5~6%で、残りはほとんど酸素で占められています。
イオンと結合する多くの官能基を持つので、主に土壌改良資材として保肥力(養分が流れないように掴まえておく力、または量)を高めたりpH変動など化学的変化を抑制する緩衝能があります。またホルモン的に根を刺激し発根促進する効果もあります。
人工的には、石炭化の進んだ“亜炭”や“褐炭”等を硝酸で分解し、石灰や苦土を加え、中和して作られたものがありますが、これは腐植酸ではなく腐植酸質資材と呼びます。
関連リンク
- 穂肥ホゴエ
- 水稲の栽培において、出穂前に施用する肥料のこと。品種や環境、生育状況により適性施肥時期は異なります。
ひとつの穂につく実の数を多くし、無効分けつを減少させ、止め葉(穂が出る前に展開する最後の葉)の生長を良くする、捻実を良くするなどの効果により収量性を向上させます。
関連リンク
ま行
- 無機化ムキカ
- 有機態の窒素が、微生物などにより無機態のアンモニアや硝酸に分解生成されること。
植物は無機態になった窒素を吸収して利用します。無機化には有機態窒素がアンモニアに分解されるアンモニア化成と、アンモニアが亜硝酸を経て硝酸に変化する硝酸化成があります。
アンモニアから亜硝酸への変化には亜硝酸菌(ニトロソモナス)、亜硝酸から硝酸への変化には硝酸菌(ニトロバクター)が関与しています。
- 無効分けつ(無効分げつ)ムコウブンケツ(ムコウブンゲツ)
- 分けつ(分げつ)して茎となっても結実しない分げつのこと。
稲は分けつ(分げつ)(茎の本数の増加)しながら生育しますが、分けつが多すぎると実がつかない茎が多くなってしまいます。
や行
該当するデータがありません
ら行
- りん酸リンサン
- 植物が最も必要とする栄養素である、肥料三要素のひとつ。肥料法では5酸化2燐(P2O5)の形で成分表示されます。
植物が利用可能な可溶性りん酸には有機質の形、弱い酸に溶ける形(く溶性)、水に溶ける形(水溶性)などがありますが、植物に吸収されるには、溶解してイオンの形になる必要があります。く溶性りん酸は植物の根から分泌される有機酸によって溶解することによりイオン化します。
はたらき:植物の光合成や呼吸作用に関与しています。また、核酸、酵素の構成要素です。
(1)成長促進(根、茎、葉の数を増やす) (2)根の伸長、発芽力を盛んにする (3)品質を良くする(花や実の数を多くする、実入りを良くする)などのはたらきがあります。
- りん酸の固定リンサンのコテイ
- 水溶性のりん酸が土壌に固定され、難溶性となる現象のこと。
りん酸の固定には鉄、アルミニウム、カルシウムとの化合による沈殿形成、土壌粒子表面における水酸基・けい酸イオンとの交換による吸収などがあります。日本の代表的火山灰土壌である酸性の黒ボク土ではりん酸を固定する力が強いため、く溶性りん酸を含む熔りんを施用したり、固定したりん酸を遊離させる力がある腐植酸入りの資材の施用をおすすめします。
関連リンク
わ行
該当するデータがありません