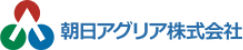農業用肥料PRODUCTS

あ行
- アルカリ分アルカリブン
- 肥料法における保証成分で、石灰質肥料などの肥料中に含まれる可溶性石灰の量、または可溶性石灰と可溶性苦土の量を、酸化カルシウムに換算した量のこと。日本の土壌は酸性の火山灰土壌が多く、酸性土壌のpH矯正の際の目安にもなります。アルカリ分が高いほど、酸性矯正能が高いです。
- 塩基置換容量(CEC)エンキチカンヨウリョウ
- 保肥力の指標であり、陽イオン交換容量ともいいます。土壌が陽イオン(塩基)を保持できる最大量を示す値のことで、土壌診断の結果として出てくる値です。
塩基置換容量が大きい程、保肥力が高いといえます。また土壌中に有機物や腐植が多いと、陽イオン置換容量は大きくなります。
か行
- キレートキレート
- キレートとは「カニのはさみ」を意味し、栄養分となるミネラルを有機物中の官能基ではさみの様に結合する形を言います。薬剤ではEDTAが有名であり、液肥では鉄や銅などのキレート物を原料として使用しています。キレートの形になると、金属の沈殿が防止され、溶解性が高まります。
土壌中では堆肥などに含まれる腐植酸によるキレート効果で微量要素などの成分を吸収しやすくなるとともに、肥料効果が高まるといわれています。
関連リンク
さ行
該当するデータがありません
た行
- 炭素率/C/N比タンソリツ/シーエヌヒ
- 土壌や有機物中の炭素(C)と窒素(N)の比率のこと。
有機物の腐熟の度合いを示すことにも使用され、未熟のものは高く、十分に分解が進んだものは低くなります。未熟な有機物を土壌に施用すると初期分解産物として有機酸等の発芽障害物質を生成したりします。
炭素化合物の割合の高い炭素率が30以上の有機物を施用すると、土壌中酸素が減少し還元状態となったり、微生物と植物との間で窒素の取り合いが起こり、植物が窒素飢餓を起こす可能性があるので注意が必要です。
- 団粒構造ダンリュウコウゾウ
- 土壌の単一粒子が集まって大きな粒子の集合体になっている構造のこと。
団粒は丸みを帯びており、有機物・石灰の多い表層土に見られます。堆肥等の有機物を施用することにより繁殖した微生物の菌糸や、植物の根からの分泌物などが接着剤のはたらきをして団粒構造の形成が促進されます。
団粒の発達した土壌はいわゆるふかふかの土で、孔げきが多く、保水力に優れ、空気の流通もよい、植物の生育にとって好ましいものです。強く圧すると崩れてしまうため、注意を要します。
- 土壌の三相分布ドジョウのサンソウブンプ
- 土壌は、固相、液相、気相の三つの相から成り立っており、各相がそれぞれ占める割合のこと。
作物の良好な生長には、土壌粒子の間に、水分と空気がバランス良く分布していることが必要です。有機物を施用した土壌では微生物の菌糸などの接着効果で団粒構造が発達し、気相、液相の割合が増えてきます。また、堆肥やピートモスなども通気性や保水力を物理的に高め、良好な三相分布の形成に寄与しています。
- 土壌微生物ドジョウビセイブツ
- 土壌中に生息する微生物の総称のこと。
放線菌、糸状菌、原生動物、線虫類などが含まれます。
窒素成分をアンモニア態あるいは硝酸態などの植物が利用できる形に変換するなどのはたらきを持っています。また有機物分解により腐植や団粒構造を作り、土壌環境を整える上でも重要な役目をしています。
な行
該当するデータがありません
は行
- pHピーエッチ
- 酸度(水素イオン濃度)のこと。
水素イオンの濃度が高いほど酸性、低いほどアルカリ性になります。pH7(中性)を境に、数値が小さくなる程強酸性、数値が大きくなる程強アルカリ性といいます。
硫酸や硝酸などは酸性を呈し、カルシウムやマグネシウムなどはアルカリ性を呈します。土壌や植物の適正pHは弱酸性~中性なので、極端な酸性やアルカリ性にならないよう、土壌診断等を活用してください。
ま行
- 無機化ムキカ
- 有機態の窒素が、微生物などにより無機態のアンモニアや硝酸に分解生成されること。
植物は無機態になった窒素を吸収して利用します。無機化には有機態窒素がアンモニアに分解されるアンモニア化成と、アンモニアが亜硝酸を経て硝酸に変化する硝酸化成があります。
アンモニアから亜硝酸への変化には亜硝酸菌(ニトロソモナス)、亜硝酸から硝酸への変化には硝酸菌(ニトロバクター)が関与しています。
や行
該当するデータがありません
ら行
該当するデータがありません
わ行
該当するデータがありません